お知らせ/ブログ
民法改正で変わる自宅の相続方法とは?
2025/08/05
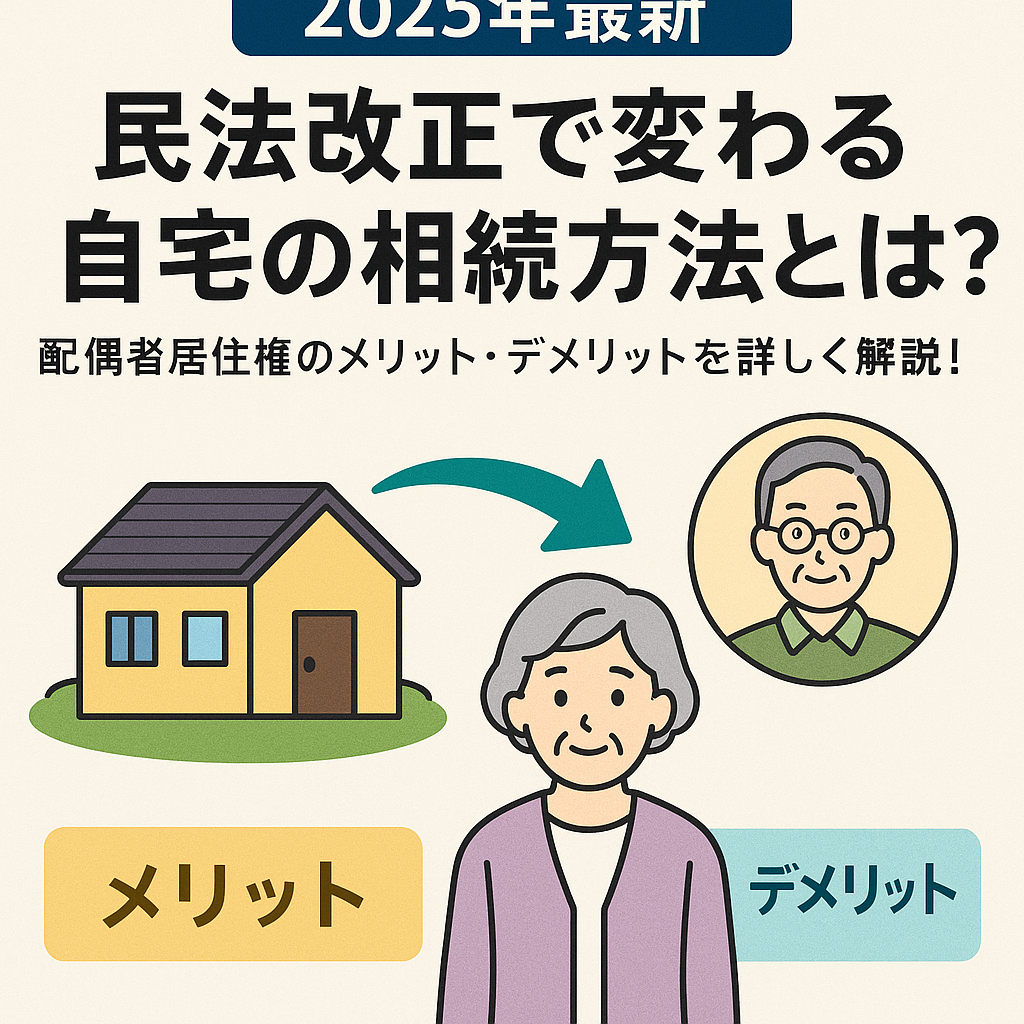
■ 相続法の大改正は2020年から適用!自宅の相続方法に何が変わったのか?
2020年4月1日から施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、自宅の相続方法に大きな変更がありました。
この改正は、1980年以来約40年ぶりの大規模な見直しであり、特に「遺された配偶者の居住権(配偶者居住権)」を新たに導入した点が注目されています。
従来の制度では、夫が亡くなった後に妻が住み続けるためには、自宅の所有権を相続する必要がありました。しかし、相続人が複数いた場合には、次のような問題が起こりがちでした:
-
妻が自宅を相続すると現金が少なく、生活資金が足りない
-
子どもが遺留分を主張して、妻に代償金の支払いが必要になる
-
相続放棄や遺贈によって、妻が自宅から退去を迫られる可能性
これらのリスクを解消し、遺された配偶者の生活を守るために創設されたのが「配偶者居住権」です。
■ 【解説】配偶者居住権とは?短期・長期の2つの保護制度
● 配偶者短期居住権:最低6カ月間は住み続けられる
自宅が誰の相続になるかがまだ決まっていない場合でも、配偶者が引き続き一定期間住み続けられる権利です。具体的には:
-
最低6カ月間の居住保障
-
新たな所有者から退去請求があっても、通知から6カ月間は居住可能
-
遺産分割協議中でも適用される
生活基盤を整える猶予期間として、配偶者の暮らしを守る仕組みです。
● 配偶者居住権:終身または一定期間の居住を保障
より長期的に配偶者の住まいを守るのが**配偶者居住権(長期保護)**です。これにより、所有権とは別に「住み続ける権利」だけを相続することが可能になりました。
具体例:
-
相続財産:自宅4,000万円+現金2,000万円
-
妻と子の2人が相続人
-
従来:妻が自宅を相続すると現金は500万円のみ → 生活資金が不足
-
配偶者居住権の活用:
-
建物の価値:配偶者居住権2,000万円
-
残りの所有権:2,000万円
-
妻 → 居住権2,000万円+現金1,000万円
-
子 → 所有権2,000万円+現金1,000万円
-
このように、妻の住まいと生活資金を両立させる分割方法が可能になりました。
■ 制度のメリット:生活基盤と財産のバランス確保
配偶者居住権の導入には、次のようなメリットがあります。
-
✅ 住み慣れた自宅に住み続けられる
-
✅ 所有権を子どもに渡しつつ、配偶者の生活も守れる
-
✅ 相続後のトラブル(売却・退去命令など)を回避
-
✅ 彦根市のような地元密着エリアでの空き家対策にもつながる
彦根市の不動産市場に詳しい【トラストエージェント】でも、こうした配偶者居住権の活用をふまえた遺産分割プランの無料相談を行っています。
■ デメリットと注意点:制度活用には専門家の関与が必要
一方で、制度の運用には以下のような注意点もあります。
-
❗ 評価額の算出が専門的:建物の築年数、耐用年数、平均余命など複雑な要素で計算される
-
❗ 固定資産税の負担者は所有者側:子どもが所有権を持ち、税金だけ負担する形になることも
-
❗ 譲渡・売却の制限:配偶者の同意が必要、認知症などで同意が取れないケースも
このため、「自分たちの家族にはこの制度が適しているのか?」を専門家と共にじっくりシミュレーションすることが不可欠です。
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

